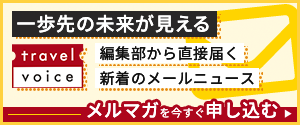空のモビリティ革命を推進するAirX社。マーケテイング ソフトウェア会社の同僚だった手塚究氏と多田大輝氏が共同で2015年に立ち上げた。航空機使用事業者向けの集客事業から始め、専用ヘリコプターによる人員輸送や遊覧飛行にビジネスを拡大。さらに、未来を見据え、「空飛ぶクルマ」の商業化に向けても積極的な動きを見せている。
より自由で価値のある空の移動へ。2人が描く未来図とは?共同創業者の両氏に、これまでの道のりと、今後目指す事業展開を聞いてきた。
始まりはヘリコプター事業者への送客支援
「移動手段がアップデートされると、人の生活もよりアップデートされて、その1人1人の人生もアップデートされていくのではないかと考えた」と、代表取締役の手塚氏は起業の原点をそう話す。2人は前職で旅行業界向けなどのマーケティングソフトウェア開発に従事していた時、業界のトレンドなどにも触れる機会があり、どこかのタイミングで、面白いことをやりたいと話し合っていたという。
そのなかで、ヘリコプターという空の移動に目をつけた。取締役の多田氏は「当時、移動領域ではウーバーなどスマホで予約決済できるサービスがすでにあったので、これを空の領域でチャレンジするのは面白いと考えた」と振り返る。
AirXは、ヘリコプター予約サービスとして「AIROS Skyview」を開発。航空使用事業者が所有・運航するヘリコプターへの集客支援を事業化した。航空使用事業者は、ドクターヘリや防災ヘリなど運航体制を自治体などに納品するというビジネス形態が主力で、ヘリコプターが遊休資産になっていたところがあるという。言うまでもなく、ヘリコプターは地上では1円も稼ぐことはできない。
AirXは、その休んでいる機体あるいは座席をシェアリングエコノミー的なモデルで埋めている。当初は、提携会社の開拓にも苦労し、「1ヶ月で1本のフライトだった」(手塚氏)。それでも実績を重ねていくうちに、提携ネットワークも拡大。現在は航空機使用事業者10社と提携している。多田氏は「こちらで集客を増やすにつれて、運航側も新たにパイロットや整備の体制を整える必要があり、供給が需要に追いつかない時期もあった」と明かす。
 「移動手段がアップデートされると、人の人生もアップデートされる」と手塚氏。鉄道会社との連携やヘリポート開拓も
「移動手段がアップデートされると、人の人生もアップデートされる」と手塚氏。鉄道会社との連携やヘリポート開拓も
並行して、AirXは、鉄道会社との連携も進める。例えば、2019年に西武ホールディングスと東京と各地のプリンスホテルを空で結ぶ輸送・遊覧を展開。第一弾は、新木場の東京ヘリポートと下田プリンスホテル間およびザ・プリンス箱根芦ノ湖間で実施し、第二弾は軽井沢プリンスホテルへの輸送と現地での遊覧飛行を実証として始めた。さらに、2021年10月には京急電鉄と資本業務提携を結んだ。
手塚氏は「鉄道会社としては、沿線人口が減ることが予想されるなか、沿線以外の施設でのインバウンドや富裕層の取り込みで、空の移動に注目したようだ」と話す。
さらに、同時進行で全国でヘリポートの開拓も進めた。輸送実績を重ねていくうちに、離着陸地を整備すると需要を増やせることが分かったからだ。手塚氏は「地権者や地元事業者と話を進めながら、夜の遊覧や観光で使える離着陸地を増やしていった。それに合わせて利用者も増えていった」と振り返る。
 「JALやANAと同じような企業価値の会社に」と多田氏。訪日客に人気の遊覧プラン
「JALやANAと同じような企業価値の会社に」と多田氏。訪日客に人気の遊覧プラン
AirXは、観光でのヘリコプター活用にも力を入れている。数々のヘリコプター遊覧飛行プランを用意。東京のみならず、大阪、横浜、富士山、北海道、沖縄など全国で展開している。例えば、東京タワー、東京スカイツリー、レインポーブリッジなどの上空を巡る15分のヘリクルージングは、1人2万2000円からと気軽に利用できる料金設定で提供している。
現在、月間で搭乗者の4割~5割が訪日客。日によっては、8割~9割にもなるという。特に富士山へのクルーズは、ほぼ外国人。手塚氏は「インバウンド搭乗者の増加率は、インバウンド旅行者全体の伸びを超えている」と明かす。
一方、日本人搭乗者は記念日など特別なイベントとしての利用が多く、カップルやファミリーがボリュームゾーン。ただ、高価な乗り物というイメージや安全性の懸念も根強いことから、「国内マーケットの拡大が課題」(多田氏)との認識だ。
また、遊覧飛行だけでなく、宿泊を合わせた商品プランの造成にも意欲を示す。手塚氏は「着地での滞在時間が延びれば、その地域の経済効果にもつながる。単に早く移動できるだけでなく、その先に付加価値をつけて、体験価値を上げていきたい」と話す。
そのためには、着地の宿泊施設や二次交通としてのタクシーなど地域事業者との連携が重要との考えだ。多田氏は「地域で何かしらのストーリーを持っている事業者と連携し、お互いの価値を高めていくとともに、利用者の人生観が変わるような旅を創出していきたい」と意欲的だ。
AirXは、旅行業登録もしていることから、将来的には自社での商品造成や催行も視野に入れている。
「空飛ぶクルマ」の社会実装に向けて着々と
AirXは、次世代エアモビリティとして、いわゆる「空飛ぶクルマ」のインフラ構築も着々と進めている。2023年8月には、兵庫県と神戸市が実施する「大阪湾ベイエリアにおける空飛ぶクルマの実機を活用した実証事業」に採択。2024年3月には、つくば航空との連携で技術実証や整備拠点として「つくば空飛ぶクルマ テストフィールド」を開設し、関東で初めて実証フライトもおこなった。
 関東初の「空飛ぶクルマ」の実証フライトは「つくば空飛ぶクルマ テストフィールド」で実施された。
関東初の「空飛ぶクルマ」の実証フライトは「つくば空飛ぶクルマ テストフィールド」で実施された。
AirXは、2018年に国土交通省と経済産業省が進める「空の移動革命に向けた官民協議会」に参画。早い段階から「空飛ぶクルマ」の社会実装に取り組んできた。
手塚氏は「すでに安全に街に溶け込む形で飛べる状態になってる。今後、機体価格も下がり、今の公共交通機関と同じような価格で飛べるようになると思う」と先を見据える。
今年4月には、航空機メーカーのエンブラエル・グループの都市型エアモビリティ(UAM)開発企業「EVE Air Mobility(EVE)」に、電動垂直離着陸機(eVTOL)最大10機を確定発注。さらに40機のオプション購入権もつけた。AirXは、2026年から2027年にかけて国内でのサービス開始を目指すという。
「10年後には、空飛ぶクルマは間違いなく一つの移動手段になると思う。空が日常に溶け込み、今の社会では考えつかないような1日の過ごし方ができて、いろんなところに住んだり、遊びに行ったり、人に出会えたりする未来ができるのでは」と手塚氏。空飛ぶクルマが空の産業だけでなく、他の産業や街も豊かになっていく未来像を描く。
多田氏は「高度数百メートルの空域では、AirXが最高の体験を届けられるトップランナーになり、JALやANAと同じくらいの企業価値として認識されたい」と意気込む。
2025年の大阪・関西万博では、4事業者が実施する空飛ぶクルマの運航が目玉の一つと位置付けられている。空飛ぶクルマを将来の公共インフラとして検討を進める自治体も増えてきた。
空のスタートアップAirXが一翼を担う空の移動革命。5年後、10年後、見上げる空にはどのような世界が広がっているのだろうか。
聞き手:トラベルボイス編集長 山岡薫
記事:トラベルジャーナリスト 山田友樹



















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】