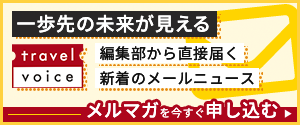近年、日本国内における外資系ホテルの存在感が一段と増しています。その背景には、訪日外国人観光客の増加や都市部を中心としたホテル需要の高まりがありますが、その一方で、人手不足が深刻な課題となっています。こうした状況の中、外資系ホテルは、どのような人事戦略を展開しているのでしょうか。IHGとヒルトンの事例を見てみましょう。
両社ともに、さまざまなプログラムがありますが、1.人材獲得、2.雇用の維持、3.人材育成、4.モチベーション向上による生産性向上などを目的の一つ、あるいは複数の達成を企図していると考えられます。
IHGが先進的な人事プログラムを導入
IHGホテルズ&リゾーツは、日本で新しい福利厚生プログラム「マイベネフィット」を導入します。従業員からのフィードバックをもとに、誕生日休暇などの新しい休暇制度を導入し、年間休日を120日提供するという方針です。
オーストラリアやニュージーランドで成功を収めた実績を参考にしながら、日本市場に特化した要素も盛り込まれています。日本の従業員から、最もリクエストの多かったのが「公正な給料」、次が「ワークライフバランス」だったため、有休の充実とともに「バースデー休暇」も新設。雇用の維持を着実にし、新規の人材獲得にもつながる取り組みです。
それ以外にも、従業員の成長を促進するため「IHGユニバーシティ」というオンラインプラットフォームで、さまざまな教育プログラムを提供しています。18カ月間で総支配人を目指す“意識高い系”社員に向けた「Journey to GM」というプログラムもあります。こちらは主に人材育成ですね。
IHGのアビジェイ・サンディリアCEO(最高経営責任者)は、「ベネフィットというのは、ホテル業界の次世代に向けたもの。日本のホテル業界がこれからも持続するように、そのために必要なプログラムだと考えている。どんどん若い人にホテル業界に入っていただいて、私達のホテルなどで仕事をしてもらいたい。訪日外国人6000万人を達成するのであれば、私たちの業界がしっかりと持続できるようになっていかなければならない」と話しています。
ヒルトンが「働きがいのある会社」第3位に
一方、ヒルトンは、Great Place to Work Institute Japan(GPTWジャパン)が発表する2025年版 日本における「働きがいのある会社」ランキングで第3位に選出されました。ホスピタリティ業界としては第1位の高評価です。
ヒルトンは、世界的にも働きやすい会社としての評価が高い企業です。世界大手ホテルの中でも、とりわけ人材活用と福利厚生に力を入れていることがみてとれます。「Thrive Hilton」プログラムを通じて、ウェルビーイングやキャリア支援に注力し、長く働き続けられる環境づくりを進めています。これは、人材育成による長期の雇用の維持を目指していると考えられます。
ヒルトンの日本・韓国・ミクロネシア地区人事統括本部のテリィ・ジェイコブス上席統括本部長は「アジア、とりわけ日本では、休みをとるカルチャーが育っていないので、きちんと有給休暇を消化させることを徹底している」と、「隗(かい)より始めよ」的な基本姿勢の大切さを説きます。また、ボランティアなど特筆すべき活動をアピールして認められれば、有休と同時に5000ドルが支給される「バーティカル」という制度もあります。モチベーションがかなり上がりそうです。
個人のワークライフバランスを充実させるためには、休んでいない従業員の負荷が増えない工夫も大切です。ヒルトンではスキマバイトのタイミーも活用して、繁忙期に対応しています。短時間バイトでも対応できるように厨房など業務の一つ一つを細かく仕分けしているため、ホテル全体のオペレーションの効率化にも役立っています。この取り組みは、従業員の満足度向上による雇用の維持につながるものでしょう。
“縁の下の力持ち”が活躍する「F&Bマスターズ」
ヒルトンの人事戦略で興味深かいのが、料飲部門の従業員を対象にした「F&Bマスターズ2025」です。
 F&Bマスターズ2025での表彰式。各受賞者の所属ホテルの方々が、我がことのように大喜びする姿も
F&Bマスターズ2025での表彰式。各受賞者の所属ホテルの方々が、我がことのように大喜びする姿も
このコンテストは、ホテルで働く料理・菓子・ソムリエ・バー・バリスタ・フォトの6部門にわたる競技会であり、全国のヒルトン系ホテルから146名が参加しました。優勝者には特別な研修や海外ワイナリー訪問といった特典が用意されています。
技術や創造性を競い合うこのイベントは、単なる競技会にとどまらず、社員同士の連携強化や士気向上にも寄与する重要な機会となっています。部門ごとに異なる専門技術を持つ従業員が横断的に交流できるプラットフォームとして機能しており、普段は接点の少ない従業員同士が互いのスキルや知見を共有し、モチベーション向上につながっています。半ば、自発的な人材育成にもなっていると思います。
全国から集まったヒルトン系ホテルの従業員が「チーム対抗戦」のように受賞者とともに一喜一憂している様子は、昭和の日本企業によくあった社員運動会などのイベントを彷彿とさせます。日本のヒルトングループでのF&Bマスターズは、世界と比較して最も本格的で長続きしているそうです。
IHGとヒルトンの取り組みを通じて見えてきたのは、グローバルの経験を背景にした柔軟性を持ちながらも、日本特有の働き方に配慮することの重要性です。外資系ホテルが持つグローバルな視点と、日本市場特有の人材ニーズをいかに調和させるか。それがインバウンド客にも国内客にも共通の、日本のホテルに求められる「おもてなし精神」を持った人材育成に役立っているのではないでしょうか。




















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】