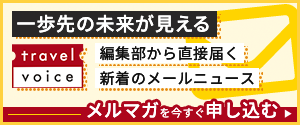今年3月中旬に南仏マルセイユで開催された「ランデブー・アン・フランス2019 (RDVF2019)」に合わせて、プロヴァンス-アルプス-コートダジュール地方では26本のファムツアー(旅行業界・マスコミ向け視察プログラム)が催行された。地域ごとではなく、いずれもテーマ別の設定。たとえば、「プロヴァンスの村々」「キリスト教の聖地巡り」「ラグジュアリートラベル」など。そのうちのひとつ「偉大な画家の足跡をたどる旅」に参加してみた。巡ったのはゴッホとセザンヌゆかりの地。テーマが明確だと、訪れる街の輪郭もくっきりとしてくる。
古代ローマ時代のアルルはゴッホの街
フィンセント・ファン・ゴッホは1888年2月、パリからプロヴァンスのアルルに移り、後世に名を残す傑作を次々に生み出した。アルルの街中にはその題材となった場所が数多く現存し、それぞれに解説付きの複製画パネルが立てられている。ゴッホの足跡を辿れば、そのまま古代ローマの面影を残すアルルの街の観光にもなるというわけだ。
1世紀末に建造されたと言われる円形闘技場からローヌ川に向かう途中に有名な『黄色い家』のモデルとなった家が今でも残る。ゴッホはここで友人のゴーギャンと共同生活をした。大喧嘩した末に、ゴッホはカミソリでゴーギャンを切りつけようとするが、自分の左耳の一部を切り落とし、その肉片を封筒に包み、行きつけの売春宿の娼婦レイチェルに渡したというのは有名な話だ。
 推定紀元1世紀末に建造された円形闘技場はアルルのシンボル。世界遺産にも登録されている
推定紀元1世紀末に建造された円形闘技場はアルルのシンボル。世界遺産にも登録されている有り余る感情のはけ口を探すゴッホにとって、南仏の明るい太陽が降り注ぐアルルは、創作意欲を掻き立てる場所であったことは間違いないようで、ゴッホ独特の強いイエローカラーがここで生まれたのも偶然ではないのだろう。かの有名な『ひまわり』もアルルで描かれた。当初は12点の『ひまわり』を描こうとしたが、最終的には7点に終わったという。
『ローヌ川の星月夜』が描かれたのもアルルだ。暗いブルーを基調に街灯の光がローヌ川の川面に揺らめき、その空には怪しく輝く星々。眩い陽を水面に照らしながら、優雅に流れる初春のローヌ川の光景からは程遠い。ゴッホは何を想い、ローヌ川の流転を眺め、筆をとったのだろうか。明るい南仏の光がありながら、わざわざ夜のローヌ川を・・・。パネルの複製画と眼前に広がる光景を見比べながらゴッホの心情に想像が膨らむ。
 ゴッホはこの場所で『黄色い家』を描いた。(左)
ゴッホはこの場所で『黄色い家』を描いた。(左) 『ローヌ川の星月夜』が描かれた場所。川の流れは今も変わらない。(右)
『ローヌ川の星月夜』が描かれた場所。川の流れは今も変わらない。(右)アルルではペインティングのワークショップにも参加してみた。いわゆるタビナカ・アクティビティ。インストラクターからゴッホの画風を簡単に教えてもらい、無謀にもその真似をしてみようというものだ。自分の気に入ったサンプルを選び、全体ではなくある部分だけを模写してみる。白いパレットに絵の具をのせ、いろいろと混ぜ合わせるが、似たような色は出ないし、筆で線を重ねて似せようとするが、やればやるほどサンプル画からは離れていく。
小学校の絵画教室以来はじめて筆をとったド素人にとっては当たり前のことたが、それはそれで自ら何かを表現する作業はおもしろい。インストラクターは「いいタッチだね。オリジナリティがある」と褒めてくれるから、図に乗ってまた色と線を重ねていくと、もはや意味も意図もない抽象画になった。
インストラクターは最後に「次の私のチャレンジは日本語を習得することです。なぜなら、この画集を読み解きたいから!」と話し、葛飾北斎の日本語の画集を高く掲げた。ゴッホが浮世絵に取り憑かれ、油絵で模写しながら、その技法を西洋絵画と融合させようとしたのはよく知られている。浮世絵だけでなく、広く日本文化や風景にも関心が高く、親交のあったフランスの画家エミール・ベルナール宛の手紙のなかでは、アルルについて「この地方は大気の透明さと明るい色の効果のため日本みたいに美しい」と書いたそうだ。ただ、ゴッホは一度も日本に行ったことはない。それでも、ゴッホを通じて日本とプロヴァンスは今でもつながっている。
 絵画の経験のある参加者は見事に模写。(左)
絵画の経験のある参加者は見事に模写。(左) 絵心がなくても筆を走らせているだけで楽しい。(右)
絵心がなくても筆を走らせているだけで楽しい。(右)アルルからゴッホが療養したサン・レミ・ド・プロヴァンスへ
アルルから北東に車で30分ほどのところにレ・ボー・ド・プロヴァンスという小さな村がある。丘の上に開けたこの村は中世には難攻不落の城塞都市として栄え、今ではフランスで最も美しい村のひとつとして観光客に人気の場所になっている。ここのもうひとつの目玉は採石場跡を活用したIMAXシアター「光の石切り場」だ。採石後にできた巨大な石の壁面にイメージを投影し、音楽とともに独特のアート空間を生み出す。訪れたときのテーマは折しも「ファン・ゴッホ」。彼の作品遍歴が重厚な音楽とともに紹介される。加えて、ゴッホと日本との関連性から後半は日本文化を表現するイメージが投影。最後は坂本龍一の『戦場のメリークリスマス』をBGMに日本らしい幽玄な演出で幕を閉じた。この演目は2020年1月5日まで催される。
 小高い丘に開けた村レ・ボー・ド・プロヴァンス。(右)
小高い丘に開けた村レ・ボー・ド・プロヴァンス。(右) 石切り場の中に広がる幻想的なアート空間。(左)
石切り場の中に広がる幻想的なアート空間。(左)さて、ゴッホは「耳切り事件」後、アルルの病院で入退院を繰り返したあと、療養のためにサン・レミ・ド・プロヴァンスのサン・ポール・ド・モーゾール修道院に入所した。発作に苦しみながらも、創作意欲は衰えず、ここでも数々の傑作を生み出す。アルピーユの山並みの上に輝く星々と三日月にS字状にうねる雲の『星月夜』や浮世絵の影響を色濃く受けたと言われている『アイリス』を描いたのもここだ。現在も修道院、教会、まわりの風景などはゴッホが入院していた当時と変わらない。ゴッホの部屋も再現され、『ファン・ゴッホの部屋』や『農夫のいる麦畑』のレプリカとともに見学することが可能だ。
 ゴッホも歩いたであろうサン・ポール・ド・モーゾール修道院の回廊(左)
ゴッホも歩いたであろうサン・ポール・ド・モーゾール修道院の回廊(左) 修道院内に再現されたゴッホの部屋(右)
修道院内に再現されたゴッホの部屋(右)セザンヌの故郷エックス・アン・プロヴァンスへ
サン・レミ・ド・プロヴァンスの西、マルセイユからだと車で北に45分ほどのところにエックス・アン・プロヴァンスという街がある。ここは、ゴッホ、ポール・ゴーギャンと並んで3大後期印象派と呼ばれたフランスの画家ポール・セザンヌが生まれたところだ。セザンヌはエックス・アン・プロヴァンス大学の法学部に入ったが中退し、絵の勉強をするためにパリに出た。何度もパリのサロンに出展するが、落選続き。失意のセザンヌは1880年代に創作拠点を故郷に移す。このころから、印象派から抜け出し、独自の世界観を構築。その後のキュビズムの基盤を築いたと言われている。
エックス・アン・プロヴァンスにはセザンヌゆかりの場所が点在する。そのひとつが街の中心から少し離れたレ・ローヴの丘にあるセザンヌのアトリエ。資産家だった父親が所有する土地に自ら設計して建て、晩年の4年間をここで過ごしたという。現在も1906年にセザンヌがその生涯を閉じた時の状態で保存されており、2階の制作部屋にはイーゼルや絵の具などが当時のままの状態で展示されている。テーブルには偽物のフルーツや古びたグラス、ワインボトルなども何気なく置かれているが、それがセザンヌの世界観をうまく表現しており、見ているとまるでセザンヌの静物画のなかに迷い込んだような錯覚を覚える。
ゴッホと親しかったエミール・ベルナールはセザンヌも慕っていた。ベルナールの著書によると、晩年のセザンヌは規則正しい生活を送っており、毎日午前中に街の自宅からこのアトリエに通い、多くの静物画、風景画、肖像画を描いた。特に力を入れていたのは大水浴図。ガイドの話だと、壁に取り付けられた長細いドアは、その絵を出し入れするために取り付けられたという。
 セザンヌの息遣いが聞こえてきそうなレ・ローヴのアトリエ(左)
セザンヌの息遣いが聞こえてきそうなレ・ローヴのアトリエ(左) 日曜日のエックス・アン・プロヴァンス。マルシェは人で賑わっていた。(右)
日曜日のエックス・アン・プロヴァンス。マルシェは人で賑わっていた。(右)アルルからレ・ボー・ド・プロヴァンス、サン・レミ・ド・プロヴァンス、そしてエックス・アン・プロヴァンスを巡ったゴッホとセザンヌの足跡をたどる旅。3月でも南仏の陽光は明るく強かった。心を病んだゴッホも、失意のなか故郷に戻ったセザンヌも、この光にどれだけ助けられたか。
物語性がある旅は、想像を刺激するし、記憶にも残るし、何かのきっかけを与えてくれるかもしれない。ツアー同行者のひとりはセザンヌのアトリエでこう言って笑った。
「私も、ちょっと絵を始めてみようかしら」。
取材・記事 トラベルジャーナリスト 山田友樹


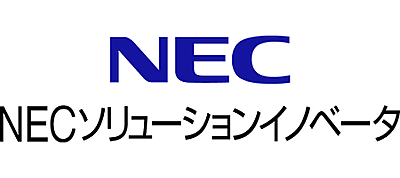
















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】