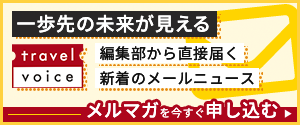EYストラテジー・アンド・コンサルティング(EY Japan)は、2025年4月23日、最新レポート「ツーリズムにおける高付加価値化は何をもたらすのか?」を発表した。レポートでは、高付加価値旅行者の動向を分析し、地域経済に及ぼす影響を考察。効果的な価値提供への取り組み方を提案した。地域が高付加価値化に取り組むことで、観光産業だけではない、あらゆるプレイヤーを巻き込み、新しい市場や産業を創出する可能性も展望している。
EY Japanのストラテジックインパクト パートナー平林知高氏は、発表の会見で、今回のレポートの背景として観光の好況な推移が続くなか、一部地域でオーバーツーリズムなどの課題が発生していることを指摘。「質の維持が叫ばれ、政策にも高付加価値化が掲げられている。いま改めて、高付加価値化とは何かを見直し、その本質を問いたい」と説明した。
高付加価値旅行者の定義と動向
日本政府観光局(JNTO)は「高付加価値旅行者」を、訪日旅行1回あたりの総消費額が1人100万円以上の旅行者と定義している。2019年の訪日外国人旅行者のカード決済データの利用人数から、その該当者を計算すると「当時は約12万人が訪日していたのでは」と平林氏は推測した。
さらに同データの平均消費単価(1人あたりの消費額)を見ると、全体平均では6万円だが、総消費額100万円以上の訪日客の場合は152万円と大幅に増加。総消費額300万円以上に限ると630万円超に達する。ただし、消費の内訳は「モノ」が中心。地域に経済効果をもたらすには、「地域の“モノ”や“体験”」へ消費が転換されることが重要だ。
平林氏は、観光庁の高付加価値旅行者の定義「単に消費額が高いだけではなく、文化や歴史、自然などの体験を通じて、自分にとってプラスになることを好む客層」を紹介。こうした旅行者は、2つの大きなトレンド「ウェルネス志向の高まり」と「伝統産業・歴史文化への関心」があり、これらは「日本の、特に地方の強みを発揮できる分野」と指摘した。
高付加価値化へのアプローチと、日本の地域にもたらすもの
レポートでは、これら2つのトレンドについて、成長可能性や日本での潜在性の高い領域、地域経済や産業に好循環をもたらす可能性を説明。高付加価値化に向けては「(旅行者が)なぜ、その地域を訪れてまでその体験をしたいと思うか。地域固有の唯一無二性の発掘・構築と、それを想起してもらうための発信・仕掛けが重要」と話した。
また、取り組みにあたっては「価値提供の観点では『人』の価値が重要」と説明。“特別な”場所や時間、体験といった「コンテンツ」起点では、そのコンテンツのある地域に限定されてしまうが、「人」を起点としたアプローチをすることで「従来、特別なコンテンツがないと思われていた地域も高付加価値化ができる」と話した。この「人」とは、地域の観光ガイドはもちろん、地場産業の職人や地域に住む作家、地域に関する研究者などだ。
平林氏は「彼らの専門知識によって、地域資源の価値が発掘される。観光産業に限らず、あらゆるプレイヤーが参画できることが、高付加価値化の大きな魅力」と説明。新たなプイヤーの参画によって、高付加価値の新市場や新産業が創出される可能性があるとみている。
平林氏は、高付加価値化は「衰退しているものや忘れ去られているものに、実は魅力がある。それを再発見して、価値を理解いただくこと」とも説明。旅行者が体験を自分の中で消化して日々の生活や仕事に生かす。それを再度、見つめ直したいと考えて再訪したり、その価値を第三者に推奨する。このサイクルで「日本の隅々まで価値を知ってもらい、地域での消費を促す好循環につながる。それにより、地域の誇りを醸成し、さらなる価値向上につながる」と話した。




















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】