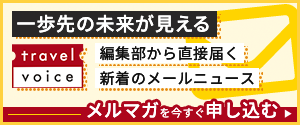観光庁は、2021年度から実施している「DX (デジタルトランスフォーメーション)の推進による観光サービスの変革と観光需要の創出事業」の成果報告会として「Next Tourism Summit 2022」を開催し、6実証事業者による成果報告とともに、「先進的な観光。地域活性化とデジタルの取組」をテーマとしたキーノートセッションを行なった。
キーノートセッションには、メルカリ取締役会長で鹿島アントラーズCEOの小泉文明氏、分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」を開発したオリィ研究所共同設立者兼COOの結城明姫氏、観光庁観光地域振興部観光資源課新コンテンツ開発推進室主査の山崎英輝氏が登壇。デザイン会社「フランコ」CEOの山田ヤスヒロ氏をモデレーターに観光産業におけるデジタル化の課題や地域活性化に求められることについて意見が交換された。
地域の魅力や価値の再定義を
セッションのテーマのひとつがDX。観光産業ではDXへの模索が続いているなか、小泉氏は「まだ議論はIT化にとどまっている」とし、DXの前にまず取り組むべきことは、Corporate Transformation の「CX」と指摘。「たとえば、押印をデジタル化する前に、それが本質的に必要かどうかを議論すべき」と強調した。
そのうえで、観光DXにおけるその本質とは「地域の魅力や価値とは何なのかを再定義し、その認識を共有すること」と提議。「それがなければ、DXがバズワード化するだけで、意味がなくなってしまう」と話した。
また、小泉氏は、観光による地域活性化のなかで、自身が率いる鹿島アントラーズを「強いコンテンツ」と位置づけ、試合前、試合当日、試合後のジャーニーを重視していることを明かした。公式アプリを通じて、そのジャーニーのポイントごとにデジタルを活用し、スタジアム来場者のデータを取得しながら、リピートにつなげていくためにジャーニーの改善を進めていき、「地域での感動値の最大化を図っていきたい」との考えを示した。
 鹿島アントラーズCEOの小泉文明氏
鹿島アントラーズCEOの小泉文明氏
また、結城氏は、分身ロボット「OriHime」による取り組みについて言及し、「遠隔で楽しむだけでは、地域に経済的価値は生まれにくい」として、ジャーニーの一環として、次に訪問するモチベーションを高めていく重要性を指摘。実際に、ある高齢者施設では、OriHimeを活用したオンライン墓参りを体験したのちに、実際に墓参りに足を運んだケースも見られたという。
山﨑氏は、DXは手段とし、その目的をはっきりさせることが大切と主張。「誰がユーザーなのか、誰に来て欲しいのかを考えるのが一番大切なのではないか」と問題提起した。
これに対して、小泉氏は「地元がいいと思うポイントと旅行者がいいと思うポイントは違う。ターゲット層を入れないで、地元の人たちだけで議論をすると、ジャーニーのポイントがずれてしまう」として、多面的な議論の場が必要との考えを披露した。
結城氏も、小泉氏の意見を受けて、オンライン配信でのターゲティングについても、「観光地の風景を配信するだけでなく、『何を伝えるのか』『旅行者が何を見たいのか、何したいのか』などを表現できる方法を取るべきなんだろう」と発言した。
オンライン配信については、小泉氏は「補完」と位置付けたうえで、「スタジアムが盛り上がらないものを、オンラインで配信しても盛り上がらない。観光においても、その地域に熱量がないと、デジタルで配信しても伝わらない。結局は、その地域の本質的な価値は何なのかが問われる」と持論を展開した。
 オリィ研究所共同設立者兼COOの結城明姫氏
オリィ研究所共同設立者兼COOの結城明姫氏
DXのベースはデータの取得と共有
アントラーズの課題のひとつが、鹿島市やその周辺での現地消費が伸びないことだ。スタジアムでサッカーの試合を観戦するだけで、帰ってしまう。アントラーズの場合、スタジアム来場者の55%が県外からのサポーターで、90分の試合を片道平均95分かけて見にくるという。
小泉氏は、その課題解決に向けて、「アプリなどを使って、町に人を引っ張り出すモデルを作っていきたい」と話す。
そこで、カギとなるのが顧客データだ。「DXのベースはデータ」と小泉氏。アントラーズでも「データが取れるようになって、やっとそれを利活用していくフェーズに入った」と明かす。
今シーズンの開幕戦では、コロナ禍での集客のため、一定数の無料チケットをデジタルで配布したが、すべてにJリーグIDを紐付けた。これにより、来場者の属性データを取得することが可能になり、「今後のマーケティングにつなげられるようになった」という。
また、混雑回避を目的に、NECとの協業で入場やスタジアムの決済を顔認証で行う取り組みも始めた。ここもデータ取得機会になる。
データが集まれば、サッカー以外の楽しみを仕掛けることも可能になる。たとえば、家族でカシマスタジアムを訪れても、現地では試合を見る父と息子、他のアクティビティを楽しむ母と娘などが別れてもいい。小泉氏は「極論を言えば、スタジアムに来てもらえる人はサッカーファンでなくてもいい。サッカーファンだけの議論をする必要はない」と明快だ。
観光庁の山崎氏も「データ取得は最低限やってもらいたい」と話したうえで、地域でそのデータを共有する重要性を指摘する。「地域では、宿泊施設、交通、飲食などさまざまな事業者が関係しているので、いろいろな目線で旅行者の動きを見ていくことが大切」との考えだ。結城氏も、データのインフラ化を訴えた。
ただ、事業者間の連携に加えて、個人情報提供に対する抵抗感という課題もある。小泉氏は「渋滞の回避やストレスのない決済などはみんなが求めていること。(データ取得は)試合日だけと限定することで、社会実装のきっかけになるのではないか」と提言。結城氏は、OriHimeが盗撮の道具になってしまう懸念に対して「悪意がないことを丁寧に説明していけば、分かってもらえる」と前向きな姿勢を示した。
 観光庁の山崎英輝氏
観光庁の山崎英輝氏
多面化するペルソナとストーリー
デジタルが浸透したことで、マーケティングや流通の手法が変化しただけでなく、「ペルソナも多面的になっている」との意見もパネリストは共有した。
小泉氏は「従来のTVや雑誌のような片方向の情報発信での旅行の選び方と、SNSなど双方向での旅行の選び方では全然違う。昔のようなペルソナは通じなくなってきている。世代や男女などのペルソナはあまり意味がなくなってきたのではないか」と話し、小手先のマーケティング論が通じなくなっているとの認識を示した。
一方、結城氏は、コロナ禍で巣篭もりやリモートが広がったなかで、「孤独を知った人は多い。だからこそ、人の温かさをもっとポジティブに捉えられるようになったのではないか」と話し、デジタルだけでない、アナログの重要性も指摘した。
ペルソナと同時に旅行者が求めるストーリーも多様化している。「エリアごとに魅力を伝えることは通じなくなってきている。デジタル世代の若者は、もっとポイントとポイントで見ている」と小泉氏。ポイントで入り、そこが結果的にそのエリアだったという構図の方が「今の消費者には合っているのではないか」と話す。
結城氏も「ポイントは切り取り方」と続ける。「男女でもないし、世代でもない、ペルソナに合わせたストーリーの伝え方をしていく必要があるのではないか」と提言した。
セッションでは、シビックプライド(地元市民の地域に対する誇り)についても意見が交換された。モデレーターの山田氏は、地元福岡市の「全力接待」を挙げ、「食や人を観光資源にして、訪問者に好きになって帰ってもらう。自分の町が好きだから」と話し、観光にはシビックプライドか大切ではないかと問題提起した。
小泉氏は「シビックプライドはすべてのベース。旅行者は非日常を求めているなかで、それがなければ、地域に訪れる人の気持ちも高ぶらない」としたうえで、「人は心の豊かさをこれからますます求めていくのだろう。地域はさまざまな魅力があるのに気づいていない。もう一度、そこを再定義したうえで、デジタルを使っていくと明るい観光産業になるのではないか」と提言。本質的な地域のライフスタイルを掘り下げていく必要性を説いた。
 モデレーターを務めた「フランコ」CEOの山田ヤスヒロ氏
モデレーターを務めた「フランコ」CEOの山田ヤスヒロ氏
「開発事業」と「活用事業」の6つの実証事業
報告会では、「DX の推進による観光サービスの変革と観光需要の創出事業」に採択された17実証事業者のうち6実証事業者が、事業内容と成果を報告した。この事業は、「これまでにない観光コンテンツやエリアマネジメントを創出・実現するデジタル技術の開発事業」と「来訪意欲を増進させるためのオンライン技術活用事業」に分けられる。発表された6つの実証事業は以下の通り。
- 富士山エリア観光DX革新コンソーシアムによる「顔認証と周遊eチケットを融合した手ぶら観光の実現(開発事業)」
- コンフォートデジタルツーリズム事業化推進協議会による「5G自動運転・xRが創る「どこでもテーマパーク」(開発事業)」
- にっぽん旅先ぐるめプロジェクトによる「オンライン技術を活用した「日本全国の美味しい体験」プラットフォーム構築による来訪意欲促進実証事業(活用事業)」
- 青森オンライン魅力発信協議会による「青森の夏・秋・冬の多彩な魅力を発信・交流するオンライン体験イベント事業(活用事業)」
- 瀬戸内市観光振興オーナー育成プロジェクト実行委員会による日本刀の聖地・瀬戸内市オンライン文化振興オーナー育成プロジェクト(活用事業)」
- 高知県バリアフリーアドベンチャーツアーコンソーシアムによる「高知バリアフリーアドベンチャーツアープロジェクト(活用事業)」


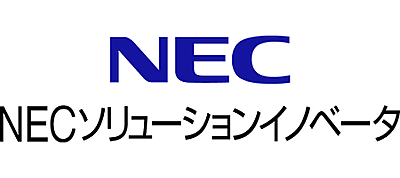

















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】