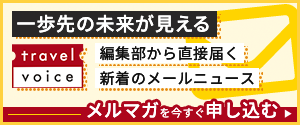この十年で約2倍の規模に拡大した、日本のクルーズ市場。2025年以降は、さらなる飛躍が見込まれている。要因は、日本のクルーズ会社による新客船の就航や、日本企業による新規参入が控えていること。その先陣を切ったのが、「にっぽん丸」で親しまれている商船三井クルーズだ。2024年12月に新クルーズ船「MITSUI OCEAN FUJI(三井オーシャンフジ、乗客定員458人)」を就航した。
これに先立ち、親会社である商船三井は、クルーズ事業を成長分野として注力する方針を決定。2023年8月、商船三井クルーズは、旧「商船三井客船」から社名変更し、同10月にクルーズ事業のブランド「MITSUI OCEAN CRUISES(三井オーシャンクルーズ)」を立ち上げた。2隻の新客船の建造も表明している。
なぜ今、クルーズ事業への投資を強化するのか。商船三井クルーズが見出した商機と差別化のポイント、新しい客層誘致の手ごたえは? 代表取締役社長の向井恒道氏に聞いた。
日本のクルーズの現状と、事業の拡大方針を決めた理由
商船三井クルーズが新クルーズ船を就航するのは、1990年に「にっぽん丸(乗客定員422人)」を就航して以来、34年ぶりのこと。また、同社が2隻体制で運航するのは、2002年に「にっぽん丸」の姉妹船「ふじ丸」を、日本クルーズ客船社との合弁による日本チャータークルーズ社に転籍してから、22年ぶりのことだ(「ふじ丸」は退役済、日本クルーズ客船社、日本チャータークルーズ社は事業終了している)。
なぜ今、長年「にっぽん丸」の1隻で運航していた同社が事業を急拡大するのか。
きっかけは、コロナ禍だ。親会社の商船三井が「コロナ明けには、人とお金の流れが大きく変わる」(向井氏)と、改めてグループ事業を総点検した。
商船三井の事業の根幹は海運業だが、クルーズやフェリー、旅行、不動産など、同社が非海運と位置付ける事業の歴史も長い。「これらの中には、人にフォーカスし、人のための空間を提供する事業も多い。今後はこれらも強みとして、付加価値を高めて発展を目指す判断をした」(向井氏)。
そこで2023年4月、人にフォーカスする事業の傘となる「ウェルビーングライフ営業本部」を発足。その中で、クルーズは「大きな投資をしていく事業の1つ」(向井氏)と位置付けた。日本のクルーズ市場に成長余力があると見たからだ。
クルーズライン国際協会(CLIA)によると、世界のクルーズ乗客数は2009年から2019年の10年間で1000万人増の2970万人に成長。コロナ後の2023年には、2019年を200万人も上回る3170万人に拡大した。2027年には3970万人に達するとの予想もされている。
一方、日本人の乗客数は、最多となった2019年で約35.6万人。2009年の約16.5万人から倍増したが、これを牽引したのは外国船社による日本発着クルーズだ。この間、日本船社の客室数が増えることはなく、2023年の初めに日本クルーズ客船が運航を終了した後は、商船三井クルーズの「にっぽん丸」と郵船クルーズの「飛鳥Ⅱ」の2隻に限られていた。
向井氏は、この状況を踏まえて同社が商機を見出したポイントを、こう説明した。
「欧米のクルーズ先進国では、人口の3~5%が乗船している。クルーズは産業として成熟期にあり、しっかりとした規模の経済が働いて、成功している企業も多い。海外の乗船率を日本の人口に当てはめると300万~400万人になる。当社の『にっぽん丸』は毎年2.5万~3万人の乗船があるが、既存の顧客層に加え、幅広い年齢、属性への認知を広げ、様々なタイプの商品を出せば、多くの方に乗船いただけると判断した」。
日本のクルーズ市場は若い世代も増えてきたとはいえ、圧倒的にシニアのリピーターが主力。新しい客層の獲得は、業界全体の長年の課題だ。
向井氏は、働く世代や若い世代にも「日本は可処分所得に余裕があったり、資産のある人は多い。国内外の素晴らしいものを経験している人が100万人単位でいるが、クルーズの魅力を伝えきれていない」と、新客層を獲得できる余地があることを説明する。
 商船三井クルーズ 代表取締役社長 向井恒道氏
商船三井クルーズ 代表取締役社長 向井恒道氏
新しい時代の日本のクルーズに
新たなクルーズ船を導入するにあたり、同社はラグジュアリークラスとして知られる米国のシーボーンクルーズ社の全室スイートの客船「シーボーン・オデッセイ」(2009年就航)を購入。この船を、日本船社である同社のクルーズ船へとリノベーションした。日本の造船所で日本向けに造られた「にっぽん丸」とは異なる外国生まれの船の特性を生かし、「『にっぽん丸』とはまた違った楽しみを提供する」(向井氏)と決めた。
例えば食事は、4つのダイニングを設置。これまでの同社のクルーズ船になかった、ビュッフェスタイルのレストランも用意した。エンターテイメントでは大きなシアターをいかすべく、船上のショーで数々の受賞歴のあるベリンダ・キング社のプロダクションショーを導入した。
「お客様がそれぞれ自由に選択できることにフォーカスして、いつでも複数の“楽しみ”を提供する。そして、船内イベントのスケジュールは、客室テレビや共有スペースのディスプレイなどデジタルでも確認できるようにした」(向井氏)。
もちろん、従来の強みや日本船社らしさも反映。「にっぽん丸」で人気の落語の公演(寄席)はもちろん、評価の高い食では洋上初となる三國清三シェフ監修の有料レストランも設けた。
このほか、フロントやカフェなどが集まった共用エリアにはコワーキングスタイルのロングデスクと電源を付け、PC作業ができるワーケーションが可能な場を設けた。働く若い世代を狙う「三井オーシャンフジ」ならではの取り組みだ。
新クルーズ客船「MITSUI OCEAN FUJI(三井オーシャンフジ)
販売状況、若い世代の獲得に手ごたえ
向井氏によると、就航から2025年の初めまでの予約は「にっぽん丸」のファンであるリピーター顧客が比較的多い。既存顧客の中心はシニア層だが、若い世代の予約も集めた。そのうち半分は、クルーズ旅行が初めての乗船客だった。
向井氏は「全体の10~15%くらいはクルーズが初めて、かつ、新しいクルーズ船が出ることに興味を持った若い世代」と、手ごたえを感じている。新しい客層からは「各地の寄港地に行けて、宿泊も食事も全部入っている。こんなに良いレジャーはない」と、喜ばれているという。
クルーズは運航日数や実施時期によっても、客層が異なる。向井氏は「にっぽん丸」の場合、1泊や2泊のクルーズは「予約が埋まるスピードが速い」とし、この需要は若い世代にもあると考える。一方、外国船籍である「三井オーシャンフジ」は、カボタージュ規制に沿って海外の寄港地に立ち寄る必要がある。今後、日本船籍に切り替える予定だが、それまでは週末や祝日とその前後2日程度の年休取得で海外の寄港地にも行ける中~長期の旅程を組んでいく。保有船の特徴をいかし、商船三井クルーズとしてバラエティに富んだ商品構成にする考えだ。
 商船三井クルーズ 代表取締役社長 向井恒道氏
商船三井クルーズ 代表取締役社長 向井恒道氏
日本のクルーズに求められる役割、インバウンド比率は約2割
「三井オーシャンフジ」の開発でこだわったのは、船のハードだけではない。寄港地観光にも注力している。地域に喜ばれる船会社であるべく、寄港地側である各港湾や観光協会と連携して商品化しているという。
例えば、香川県坂出港の寄港地観光では、弘法大師(空海)誕生の地といわれる善通寺を僧侶の案内で特別拝観するツアーを現地の提案で実現した。国の重要文化財の五重塔を三井オーシャンフジのツアー客だけに特別に開扉する。「地域の皆さんに『また来てほしい』と思われるツアーであることを目指している」と向井氏は強調する。
「当社のクルーズ船は全長200メートル以内の小型船なので、日本のほとんどの港に入れるのが強み。『にっぽん丸』は就航34年の歴史のなかでクルーズ船が入れない港以外、ほぼすべてに寄港しており、寄港地との関係性も強い。船から見る陸の風景は、また違う美しさがある。地域に貢献し、島国・日本を再発見していただくクルーズでありたい」と力を込める。
当然、インバウンドも視野に入れている。ゆくゆくは全体の2~3割にまで外国人比率を引き上げたい考えだ。「日本が主要マーケットであることは、今後も変わらない。日本のお客様を大切にしながら、外国のお客様を迎える。コンセプトである『日本の美しい船旅』を感じていただくには、全体の空気感も重要だと思っている」(向井氏)。
日本のクルーズ市場は新たな展開を迎える。同社は今後、2隻の新客船を建造する予定。ライバルの郵船クルーズは2025年にLNGを含む3種の燃料に対応したエコシップの新造船「飛鳥Ⅲ」を就航し、「飛鳥Ⅱ」との2隻体制とする。さらに、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドがクルーズ参入を表明。2028年度から「ファミリーエンターテイメントクルーズ」と銘打ったショートクルーズの運航を計画している。
向井氏は「船旅の機会が増え、すそ野が広がる。私は、クルーズが多くの人が経験するレジャー、バケーションになると確信している。クルーズ業界の未来は明るい。その需要を増やす一翼を担っていきたい」と考えている。
聞き手:トラベルボイス編集部 山岡薫
記事・写真:山田紀子


















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】