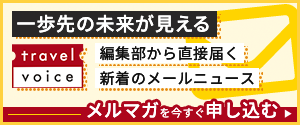成長を続けるインバウンドの恩恵を受けたいと多くの事業者や地域が集客の策を講じる一方で、日本人との習慣の違いから受入れに積極的でなかったり、思いがけない行動への対応に苦慮している声も聞かれる。
先ごろ、公益財団法人日本交通公社の「旅の図書館」リニューアル第1回特別企画「たびとしょcafe」に登壇した「澤の屋旅館」館主・澤功氏の講演には、そんなインバウンド受入れにジレンマを抱える関係者にとって、解決のヒントとなるようなメッセージが含まれていた。
英語力・外国人接客経験ゼロのスタートから、どのように言葉と文化の壁を越え、外国人旅行者の圧倒的な支持を得ているのか。澤氏の講演のなかから、同旅館と地域が外国人に喜ばれる理由をまとめてみた。
歓迎の心は雰囲気に出る
東京の下町・谷中で、外国人の個人旅行者に人気の宿として有名な「澤の屋旅館」。全12室、うちバス・トイレ付き2室の家族経営の旅館で、宿泊料金は1泊朝食付き(夕食なし)の1室5400円~。宿泊客の約9割が欧米豪を中心とする外国人客で、訪日客の宿泊を開始した1982年から昨年までに97か国地域の延べ17万7035人を受け入れてきた。
利用客の評判も良く、リピーター率は約3割。クチコミサイト「トリップアドバイザー」が高評価の施設に与える「エクセレンス認証」も2011年から5年連続で受賞し、現在も同サイトに掲載される東京都764軒の宿泊施設で1位となっている。
そんな澤の屋旅館も、受入れ当初は外国人客に対するおもてなしは試行錯誤の連続だった。有名な“単語英語”対応も、英語が堪能でない接客のなかで定着したもの。発音やイントネーションが分からない澤氏が文章で話すより、単語で伝えた方が“Your English is clear!”と言われ、自信がついた。さらに、英語ができないフランス人夫婦が1か月の滞在を終えて帰国した後、その子供で同旅館の近所に住む留学生に「とても喜んでいた」とお礼を言われたことも、自信を深めた。
澤氏としては言葉の意思疎通がなく、何もおもてなしができなかった気持ちがあったが、「言葉は通じなくても、歓迎が伝わってきた。差別の気持ちがあると体が逃げたり、目をそらしたり、内緒話をする。そういうのは雰囲気でわかる」と話していたという。このとき澤氏は、「どんな流暢な言葉よりも、誰に対しても『よくいらっしゃいました』と思う心の方が大切なのだ」と実感したという。
 澤の屋旅館の館主・澤功氏。観光庁の観光カリスマ(下町の外国人もてなしカリスマ)や、日本政府観光局のVISIT JAPAN大使にも任命されている
澤の屋旅館の館主・澤功氏。観光庁の観光カリスマ(下町の外国人もてなしカリスマ)や、日本政府観光局のVISIT JAPAN大使にも任命されている習慣の違いを理解
また、荷物を部屋に運ぼうとすると「No thank you」と断られたり、宿泊客に用意したプレゼントが持ち帰られずに捨てられるなど、日本流のサービスや良かれと思ったもてなしが受け入れられず、怒られることも。気落ちするところだが、理由を聞いてみると、荷物運びが断られたのは日本にチップがないことを知ってのこと。プレゼントについては、「(世界)195か国の人が喜ぶ共通のものはない。その代わり宿泊料金はできるだけ上げずに、頼まれたことを一生懸命対応しよう」と考えを切り替えた。
これ以外にも、和式トイレや大浴場の利用の仕方など、“訪日あるある”的な仰天のエピソードはもちろん澤の屋旅館も経験している。「無理なのかな…」と思うこともあったが、受け入れているうちに宿泊客に悪気はないことが分かってきた。自国でのいつもの習慣通りにしていることだ。だから「感情の折り合いをつければいいと思っている」と澤氏。日々、文化習慣の違いにあたりながら、その時に対応を考えるようにした。
こうした接客を宿泊客はどう受け止めていたか。澤の屋旅館に届いたサンキューレターを立教大学の大学院生が調査分析をしたところ、“Thank you for…”の後の言葉は“your service”ではなく、“hospitality”、“kindness”、“helpful”が続いていた。これについて澤氏は、「無我夢中でやっていたのをホスピタリティとして受けてくれていた。一生懸命おもてなしをすると、こういう風に見てくれる」と受けとめているという。
さらに、同調査による論文によると、サンキューレターには「ホストのホスピタリティが日本を特別の思い出の場所となるようにしてくれた」「日本を再び訪れたいと思うようにしてくれた」など、日本を理解する手助けに対する感謝が述べられていたのが特徴的だという。これについて澤氏は、「地域との取り組みでこういう評価を受けたのでは」と見ている。
ありのままの日本の姿を
澤の屋旅館が地域との関わりを持つようになったのは、夕食の提供をやめる決断をした時。外国人客は夕食を宿でとらない場合が多かったため、エリアマップを作成して、旅館ができないことは地域で楽しんでもらうことにした。外国人旅行者が街に出るようになり、地域とのつながりができるようになると、「澤の屋にないものが街にはある。地域があるから長期の旅行者の受入れにも自信がついた」と、外客受入れにとって地域の重要性を認識した。
一方、地域である谷中の街の反応だが、外国人旅行者が街に出るようになってもあまり変わらなかった。豆腐屋の商いの様子を見るのを阻むことはなく、家の前での盆栽の手入れを見られるのを嫌がることもなく、町内の祭りでも一緒に神輿を担ぐ。来る人を拒まず、けれども特別扱いをしない。ありのままの姿で誰でも受け入れ、自然と交流が生まれた。澤の屋旅館が外国人宿泊者に行なったアンケートには、「谷中には日本人の生活が残っている。そこに日本の歴史・文化があるから良い」とのコメントが多かったという。
江戸時代の寺町の風情が残る谷中は、外国人が好む魅力を持つ優位性がある。しかし、澤氏は「訪れた焼き鳥屋は混んでいたが、カウンターを詰めて座らせてくれた。焼き鳥は高かったが美味しかったし、日本の人といろんな話ができた」という宿泊客のエピソードを紹介。「これは、そのままの日本の街の中に入れてもらえたことがうれしかったということ」と、日本人の生活体験が求められていることを説明する。そして、彼らは「街に外国人を呼ぶために何かを作ろうと思わないで。今あるものを壊さないでほしい」というメッセージも発しているという。
「外国人が見たい日本と、日本人が見せたい日本にはギャップがある」。これはロンリープラネットのライターも指摘しているが、澤氏も警鐘を鳴らす。澤氏は、「外国人旅行者は訪問先の生活の中に入りたいと思うのだから、ありのままの形で受けてあげればいい。澤の屋旅館のマニュアルは公開するけれど、同じものは喜ばれない。自信をもって違うものを売ってほしい」と訴える。
「観光は平和へのパスポート」を胸に
これほど外国人宿泊客へのおもてなしを考えている澤の屋旅館だが、受け入れを決めたのは家族を養うという生き残るためのストレートな理由だった。国内の経済成長による旅行スタイルの変化や宿泊施設の多様化、交通インフラの変化などに伴い、同旅館に宿泊する日本人が激減。家族経営に縮小したものの、宿泊者数ゼロが3日続いた切実な状況のとき、「日本人が来なくなったら、外国人を受ければいい」との旧知の旅館のアドバイスで活路が開けた。
だから、澤氏はそのアドバイスをくれた知人への恩返しとして、1軒でも多くの旅館が外国人客を受け入られるようにノウハウやデータを公開し、講演に呼ばれれば応じる。そして、「一度、地獄を見た」という澤氏にとって、来館する旅行者はどんな人も同じように大切で、歓迎して受け入れるのだという。
今、澤氏が励みにしている言葉がある。それは旅行業界の合言葉、1967年の国際観光年のスローガンの「観光は平和へのパスポート」だ。澤氏は「日本の文化・生活を見たいという外国人を受け入れ、相互理解が深まることで平和につながる」と述べ、「家族のための旅館経営だが、それが平和につながるというこの言葉を胸に、外国人を受け入れていこうと思う」とインバウンド誘致の本質を語る。
なお、「観光は平和へのパスポート」の観点から、澤氏は民泊について「(ホストや管理者など)人に会わない、空室を埋めて利益を上げるだけの民泊はおかしい」との考え。これは講演の最後に、会場からの質問に答える形で言及したもの。澤氏は以前、ドイツで民泊を利用したが、その際はホストが同居する家の部屋に宿泊し、翌日はホストと一緒に朝食をとった。「地域の風俗を体験できる。こういうのが民泊ならいいな」と思ったという。
ビジネスで利益を上げるのと同時に、観光の持つ尊さを忘れてはならない。澤の屋旅館の軌跡は、その両輪の重要性を観光の従事者に示している。
取材:山田紀子(旅行ジャーナリスト)


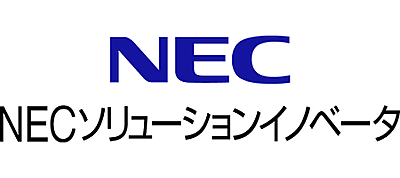

















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】