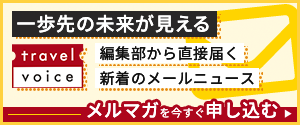デジタルノマド向けの宿泊施設を北米・南米で展開してきた「Selina(セリーナ)」が、2025年春、「Socialtel(ソーシャルテル)」にリブランドされた。ひとつの章が幕を閉じた今、同社と同じくデジタルノマドやリモートワーカー向けに事業展開していたホスピタリティ・ブランドの今後が気になるところだ。
同ブランドが段階的に消滅するニュースは、世界中でリモートワークに関する規則が逆回転するなかで届いた。とはいえ、多くのホスピタリティ・ブランドは、引き続き、ニューノーマルを追求していく方針を維持している。簡単にまとめると、セリーナは「無期限で海外に滞在し、旅行し、仕事する」ことを望むミレニアル世代およびZ世代をターゲットにしていたが、上場後、財政難に陥り、2024年7月に経営が破綻。8月にシンガポールのコレクティブ・ホスピタリティ社が買収し、セリーナの運営子会社の大部分を獲得した。
同様にデジタルノマドやリモートワーカーを顧客ターゲットにする会員制のホスピタリティ会社「Outsite」は、企業の就業規則がリモートワーク縮小へと転じているなかで、むしろ事業を拡大している。
「当社の場合、リモートワーカーの需要自体は減少していない」とOutsite創設者兼CEOのエマニュエル・ギセ氏は話す。
「減っているのは企業に勤める人からの需要で、起業家やフリーランスで働く人からの需要はどんどん増えている。過去12~18か月の間に、需要の減少というよりは『変化』が進んでいる」。
ギゼ氏は、新しいメンバーシップ・モデルを作り、アフリカやアジアなど、他の市場へと事業展開を拡大する計画だ。まず自社ブランドに合った既存ホテルを探し出し、ゲストが仕事したり、遊んだりするのに最適な機能を組み合わせ、自社施設にして運営コストを圧縮することで、実現できると考えている。
ギゼ氏は、こうした「厳選リスト」戦略について、デザインホテルの事業モデルに例えて説明する。「必ずしも、我々が運営する必要はない。要は、特定分野に強いOTAのような役割を我々が担う」と言う。
同社の戦い方は、家具付きアパートを運営するBluegroundがスタートしたパートナー・ネットワークを彷彿とさせる。精査した第三者施設と提携することで、自社にとってコア市場ではないが、供給が不足している宿泊マーケットにも対応できるようにし、成長分野を取り込もうという訳だ。
Outsiteは事業を拡大しているが、完全リモートワークを認める方針を撤回する企業は増えている。「オフィスへ戻ることの義務化」が多数を占める昨今、ビジネス・トラベルニュース・ヨーロッパは「2025年のホットリスト」として、こうしたトレンドを選んでいる。
FM:Systemsによる世論調査「Inside the Workplace Report」の2025年版では、オフィス勤務日数を週3日未満でも可とする企業は、2024年の17%から8%と半分以下に減少した。オフィス勤務は当然のことに戻りつつあり、週5日のオフィス勤務を義務付ける雇用主は57%。昨年の48%より増えている。
ドナルド・トランプ米大統領が就任初日、連邦政府機関に対し、「実行可能なかぎり早く」職員のフルタイムでのオフィス勤務を求める大統領令に署名したこと、さらに、リモートワークを承認する取り決めについて、可能なところから中止するよう指示したことで、企業ポリシーの微調整はさらに進みそうだ。
2つの世界、企業向け保養施設の需要高まる
フランスのスタートアップで、企業向け保養施設(リトリート)などを手掛けるNabooの共同創業者、マキシム・エドゥアルド氏は、ニューノーマルはすでに定着したとの見解だ。
「今は、2つの世界がある」とエドゥアルド氏は話す。パンデミック前からある世界とパンデミック後の世界だ。「少なくとも当社のクライアントの場合、リモートワークはできるだけやめる傾向にある」。
同社は最近、シリーズAの資金調達で2000万ユーロを獲得したところで、企業向けリトリート市場の力強さを伺わせる。
「コロナ禍で突然、皆がリモートワークするようになり、こうした文化が急速に拡大していった。すると今度は、皆を同じ時間、同じ場所に集める方法に悩むようになった。今のニューノーマルは、少なくとも3日間のオフィス勤務だが、今後、これが何日になっていくのかだ」と同氏は話した。
同僚と机を並べて仕事するスタイルが消えたことで失われたものもあり、これをどう補うべきかという問題もある。JPモルガンCEOのジェイミー・ダイモン氏は今年初め、ハイブリッドやリモートワーク導入により、若い社員が社会的に疎外されてしまったと話した。
ブルームバーグ報道によると、ダイモン氏は「この状況は、若い世代にとってはダメージだ」とコメントしている。
エドゥアルド氏は、こうした問題意識が企業リトリート需要にとって、もう一つの追い風になっていると指摘する。
「同僚と一緒に過ごし、お互いを知り合う時間をつくる必要がある。特に入社して日が浅い社員にとっては重要なことだ」と同氏は話す。「まだ学校を卒業したばかりなんだ」。
Nabooの本拠地はフランスだが、英国とオランダでも事業を行っており、今年はすでにスペイン、イタリア、ドイツにも進出している。
「当社はダブリンやロンドンを拠点とする大手テクノロジー企業との仕事が多く、こうした顧客の展開拡大に伴い、我々の事業も拡がっている。ギリシャ、スペイン、イタリア、ポルトガルで一泊ぐらいのリトリートの手配が多い」とエドゥアルド氏。
ギゼ氏も、Outsiteの施設をリトリートに利用する企業が増えていると話し、最長1週間ほど滞在するケースもあるという。また、リモートワークを社員向けの特典として位置づける企業もあり、例えばニューヨークのマーケティング代理店、Gradientでは、社員100人を対象に、Outsite利用を認める契約を結んでいるという。
「様々な活用方法が考えられる。むしろマーケティング的な一策として、うまく役立てているところもある」(同氏)。
マーケットを強化する
リモートワーカー向け宿泊施設への需要は、規模が小さい企業を中心に、これから増えていくのではないかとの指摘もある。Risklineで旅行情報データチームを率いるクラウディア・ガルディ氏は、老舗の大企業よりもスタートアップや小さい組織の方が、こうした方針の導入にはフレキシブルな傾向にあると以前から指摘している。
タレント・モビリティ(人材の流動性)の専門家は、オフィス勤務の必要性が高まるのに伴い、中小企業の間では、ビザを必要とする短期出張のニーズが増えると予測する。
「過去3年間で、従業員は世界中で確保できるのだと気づいた中小企業が非常に増えている。母国の外でも、費用対効果の高い労働力や必要なスキルが見つかるようになった」と、VisaDoc共同創業者兼CEOのジェームズ・トムリン氏は指摘する。
「AI(人工知能)が急速に進化する今、人と人との関係性はかつてないほど重要な要素になっており、クライアントや同僚に会いに行く海外出張は欠かせない」。
ノマドのライフスタイル
セリーナが経営を指揮したのは短い期間だったが、リモートイヤー事業部では、デジタルノマド向けのプログラム「どこでもワーク」が作られた。同部門は、コレクティブ・ホスピタリティによる買収後、2024年12月に閉鎖された。とはいえ、この出来事を取り上げて、より本格的なデジタルノマドのライフスタイルはもう飽きられてしまった、と評するのは早急との見方もある。
旅行マーケットプレイスのNaviSavi創業者兼CEO、サリー・バンネル氏は、WiFi Tribeなどの会員組織では、新しいメンバー集めに乗り出していると話す。
「デジタルノマドの中には、自身のライフスタイルを守るためなら、オフィス勤務に戻らなくても済むようにキャリアを変える人もいる」と同氏。
大企業は柔軟な働き方を見直す方向に向かっているのかもしれないが、リモート・ファーストのビジネスや、企業からのリトリート需要も拡大している。こうしたなか、デジタルノマド向けのホスピタリティは次の段階へと進んでおり、新しい形が出現しつつある。
※この記事は、世界的な旅行調査フォーカスライト社が運営する「フォーカスワイヤ(PhocusWire)」から届いた英文記事を、同社との正式提携に基づいて、トラベルボイス編集部が日本語翻訳・編集したものです。
オリジナル記事:A new phase for digital nomad hospitality amid back to work mandates
著者:マシュー・パーソンズ氏(ジャーナリスト&コンテンツ・ストラテジスト、Etude創業者)





















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】