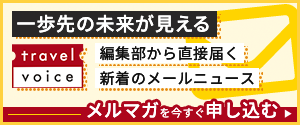日本の伝統的な宿泊施設である「旅館」。時代の変遷とともに、旅館のサービスが洋式化する一方で、ソフトやハードに和のテイストを取り入れるホテルが増えている。近年はホテルとの違いや旅館の定義自体が曖昧になってきた。
そうした中、日本旅館協会会長の呼びかけで「旅館(RYOKAN)とは何か 旅館の定義について考える」と題したセミナーがおこなわれた。UNツーリズム駐日事務所代表や大学教授らが登壇し、訪日客による旅館の利用率の低さや、外国人にわかりやすい説明の必要性などを指摘した。
訪日客の旅館の利用が低迷、特徴がわかる情報が必要
セミナーは2024年6月に日本旅館協会の会長に就任した桑野和泉氏の発案により、同氏が顧問を務める「温泉まちづくり研究会」が主催したもの。研究会は、温泉地の活性化を目的に2008年に設立され、北海道・阿寒湖温泉、群馬県・草津温泉など会員の温泉地の関係者や行政担当者、有識者などが定期的に共通課題を議論している。
桑野氏は開催の趣旨について「インバウンド6000万人時代の到来が遠くない今、旅館の定義について改めて考える段階。今日は議論を深める第一歩にしたい」と力を込めた。
セミナーには、同研究会の顧問や共同研究者を含む6名が登壇。議論に先立ち、東洋大学国際観光学部の内田彩教授がプレゼンテーションを行い、日本における近代旅館について「江戸時代の多様な宿の機能を統合し、明治に生まれた日本独自の宿泊ビジネスモデル」と説明。「近年はハード・ソフト面ともに、ホテルとのボーダーレス化が進み、差別化が難しくなっている」と指摘した。
パネルディスカッションでは、UNツーリズム駐日事務所の本保芳明代表が「2023年4月統計の平均値で、日本人の旅館の利用割合は13.2%、外国人はその半分以下の6.2%。都道府県により差はあるが、今のインバウンドの旅館利用率は非常に低い」として、利用率を上げることが急務であるとした。そして、「エクスペディアやブッキングドットコムなど、外国人が多く触れるOTAでも、旅館がどういう宿泊施設かという情報が正確に伝わってないのではないか。必要なのは、日本の旅館がどんなハードやソフトを提供しているか、外国人に明確に伝えるための整理だ」と述べた。
温泉まちづくり研究会顧問を務める阿寒観光協会まちづくり推進機構の大西雅之会長も本保氏の意見に賛同。「旅館が提供しているハードやソフトは何かを説明するには、外国人を迎える時にできること、できていないことを指標化し、各旅館がそれぞれマル、バツなどでわかりやすく示す必要があるのでは」と話した。
地域文化やストーリーを体感できる場としてアピール
日本旅館協会ミライ・リョカン委員長を務める伊豆・修善寺「新井旅館」の相原昌一郎代表取締役は、旅館を「RYOKAN」という世界共通語にすることを目指して同協会で行われた旅館の定義について「地域に根付く様々な文化を体感できる宿泊施設であり、地域文化のショーケースであること」と説明。相原氏は「地域の文化を体感できる宿泊施設であるからこそ、我々旅館は地域文化の知識を正しく獲得し、活用しなければいけないと思う」と述べた。
温泉ビューティ研究家の石井宏子氏は「旅館は日本文化及び、滞在する地域の生活文化や歴史を凝縮し、一連のストーリーとして体験できる特別な場所。インバウンドに向け、そうした要素をより強調していくべきでは」と提案した。
参加者からも「旅館は、地域のサステナブルツーリズムの中核拠点となり得る存在」「外国人に旅館の特徴を簡潔に伝えられる定型的な文章があると望ましい」などの意見が飛び交い、多様な角度から旅館についての定義や特徴、存在意義について改めて問い直す議論が会場全体で共有された。
 勉強会では、様々な意見が飛び交った
勉強会では、様々な意見が飛び交った


















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】