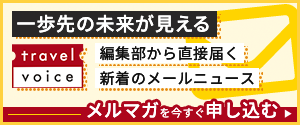訪日外国人観光客の急増により、日本の宿泊市場は大きく変化しています。東京23区や京都、大阪といったインバウンドを多く受け入れている都市ではホテルの不足が深刻化し、宿泊料金も国際都市と同様に高騰しています。こうした中で再注目されているのが、いわゆる「民泊」や「不動産賃貸型宿泊」など、これまでのホテルや旅館とは異なる考え方の宿泊ビジネスです。
もちろん、これまでも民泊やウィクリーマンションなどの形態はあったのですが、最近では、これらを細分化した新たなビジネスモデルが登場し、宿泊業と不動産業の境界がさらに曖昧になりつつあります。一方で、都市部のホテル需給を安定化させるための新たな宿泊スタイルとして、サブスクリプション型や長期滞在型の宿泊施設が注目を集めています。本コラムでは、変貌しつつある宿泊市場の現状と今後の展望について詳しく解説します。
インバウンド急増で宿泊施設がひっ迫
近年、日本への訪日外国人観光客は急増しています。特に円安の影響や日本人気が衰えない状況をみると、2025年は年間4000万人を超えるという予測も現実味を帯びてきました。そうなれば、国内の宿泊施設のひっ迫は、地域によって、さらに深刻化すると予想されます。
東京都内では、高級ホテルからビジネスホテルまで満室が相次ぎ、宿泊費が高騰しています。特に、銀座や新宿、渋谷といったエリアでは、コロナ前は平日単価が1万円以下だったビジネスホテルであっても1泊2万円以上の宿泊費が一般的になってきました。
京都市も世界的な観光地として人気が高く、観光シーズン中は宿泊予約が困難な状況です。大阪市でもインバウンド需要が旺盛で、宿泊施設数は大幅に増えたものの、エリアによっては宿泊施設の供給が追いついていません。ホテルの新規開業は続いているものの、短期間で供給不足を解消するのは難しい上、諸外国を見ても、大都市部のホテル価格が以前のような安いレベルに戻ることは考えにくい状況です。こうしたことから、これまでの価格で宿泊したいと考える層の受け皿として、ホテル以外の宿泊施設がますます注目されるようになっています。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の概要と現状
宿泊施設の不足を解決する「切り札」でもあった民泊は、2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)によって国内でも「解禁」されました。この法律は、無許可の違法民泊を規制し、健全な市場を形成することを目的としています。民泊を運営するには自治体へ届出を行う必要があり、年間営業日数は1物件あたり180日以内と制限されました。また、オーナーが不在の場合は、国の許可を受けた管理業者に運営を委託する必要があり、さらに地方自治体によっては独自の条例で営業日やエリアが制限される場合もあります。
この規制によって、本来の意義の一つであった、「個人の遊休資産を活用し、手軽に参入できる副業としての民泊」は難しくなり、むしろ大手不動産会社やホテルチェーンが多く民泊市場に本格参入しましたが、コロナ禍においてその多くが大打撃を受けたのは想像の通りです。
宿泊市場の現状とビジネスモデルの変化
一旦、打撃を受けた日本の民泊市場は、2024年度にはコロナ前の約1兆円規模まで回復すると予測されています。Airbnbの日本国内での掲載物件数は2023年時点で約6万件。観光庁発表のインバウンド消費動向調査(2024年)によると、ゲストハウス等を含む民泊を利用した訪日客の割合は全宿泊者の約11% に達しています。
地方において空き家対策や古民家活用などの名目で宿泊施設の空白地域だったエリアにも、民泊や簡易宿所登録による開業が増えてきました。しかし、年間180日の営業制限があるため安定収益を得にくく、管理や清掃の手間がかかるため個人事業主には負担が大きく、従来型の民泊ビジネスは青天井で成長していくようには見えません。
そのような中で、注目されているのが「住居として借りた部屋を、住まない日は民泊として貸し出す」という新モデルです。この仕組みでは、入居者は通常の賃貸契約を結びながら、自宅を不在時に貸し出すことができます。これにより入居者は貸し出した分の家賃負担を軽減できるメリットがあります。また、賃貸オーナーにとっても家賃収入が得られない部屋の活用も容易になるため空室リスクが低減します。不動産賃貸と宿泊のハイブリッド型ビジネスといえるでしょう。
また、不動産ビジネスにより近い形として、従来ビジネスパーソン向けだったアパートメントホテル(レジデンス型ホテルや、いわゆるウィークリーマンション)を1泊単位で利用できるようにするなど、観光客向けに仕立てて展開する動きなども進んでいます。
既存のホテル業界においても、長期滞在者向けのサブスクリプション販売が伸長しています。定額制で全国のホテルを利用できるサービスは、都市部での宿泊代の高騰の影響を避けたいビジネスマンの間で人気が高まっています。ホテルにとっても単価は安くなりますが、満室時に同系列の郊外のホテルに誘導できたり、早期予約や直前の穴埋め予約が期待できる「都合の良い利用者」の囲い込みが可能になるといったメリットがありそうです。
宿泊と居住の境界がより曖昧になる時代へ
つまり、既存のホテルはより長期滞在や居住型のビジネスへ、賃貸業はより宿泊志向へとそれぞれ裾野を広げていることで、両者の境界線が以前よりも不明瞭になりつつあります。
一方で利用者も、居住と宿泊を融合させたライフスタイルが可能になり、「半定住」「半定宿」を使い分けることで合理的に生活できる時代になってきたのです。オフィスや組織を持たないデジタルノマドや、住居を持たないアドレスホッパー、二地域居住など、多種多様なスタイルが許されるようになった時代に対応して、不動産・宿泊業界が進化してきたということでしょう。
利用者目線で考えた場合、選択肢が多いのは有難いことですが、それぞれがどんな形態の宿泊施設なのかを理解していなければ、ミスマッチが起きるでしょう。「ホテルのサービスを期待して予約してみたら、ホテルのような名前の民泊だった」など、旅行に慣れていない人には宿泊施設の選択が難しくなっているとも言えます。
初心者に向けて、それぞれのジャンルと特色がより分かりやすくなるようなカテゴライズの表現、そもそも民泊であることや、例えばマンション内であることが事前にわかるような情報提供の義務化なども今後は必要となってくるでしょう。また、民泊を含む短期宿泊賃貸(Short Term Rental)、「賃貸物件+民泊」では、防災や治安の面から時代に合わせたアップデートが必要ではないかと考えています。今、施設内に滞在しているのが居住者なのか、宿泊者なのかを周辺住民が判別できるような掲示ルールなどが求められてくるでしょう。



















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】