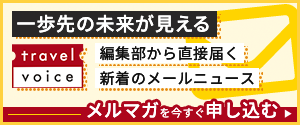オーバーツーリズムを考える京都取材(連載第2回)
日本政府は訪日外国人旅行者4000万人、6000万人を目指している。地方への誘客を進めることで、全国への需要分散化を目論むが、それでも、分母が多くなれば、それだけ京都を訪れる旅行者も増えていく。ファーストタイマーはやはり金閣寺や清水寺に行くし、多様な京都の魅力を体験しきれなかったリピーターも再訪するだろう。
第1回の『京都深掘り取材』で門川大作市長が課題として挙げた「オーバーツーリズム」への対策、街づくりのひとつとしての「民泊」。第2弾の今回は、具体的な取り組みについて、産業観光局観光MICE推進室MICE戦略推進担当部長の福原和弥氏に聞いた。オーバーツーリズムの問題意識を明文化、地域への分散を促す
京都市は今年5月、2014年に策定した「京都観光振興計画2020」をアップデートした。この4年間で京都市の観光政策を取り巻く環境が大きく変化してきたためだ。外国人宿泊客数年間300万人、観光消費額年間1兆円という目標を前倒しで達成する一方で、さまざまな課題も顕在化してきた。
そのひとつがオーバーツーリズム。
修正された「京都観光振興計画2020+1」では、市民生活と観光の調和を謳い、「外国人観光客の急激な増加とマナー問題」「無許可民泊施設の増加」「観光客の集中と混雑」を課題として挙げた。「これまで、オーバーツーリズムについて口にすることはあったが、しっかりと計画の中で明文化したのはこれがはじめて」と福原氏は明かす。
集中と混雑の対応については、時間、季節、場所の3つの分散化を進めていく方針。そのひとつの施策として、「ゆったりとした雰囲気で京都を楽しんでほしい」(福原氏)というコンセプトで『とっておきの京都、定番のその先へ』というプロジェクトを新たに始動した。そのなかで特に2つのエリアに焦点を当て、観光客の分散を進めていく。
まず、京都駅南側の伏見エリア。伏見稲荷大社は外国人旅行者が大挙して押し寄せるが、その周辺にはほとんど足を運ばないという。このエリアには、地元の酒蔵や賑やかな大手筋商店街などがあることから、外国人旅行者への訴求力は高いとして、伏見稲荷大社を訪れた外国人を回遊させる取り組みを始めた。
また、京都市では近畿圏からの日帰り日本人旅行者が近年減少していることに危機感を強めており、改めて寺田屋など幕末動乱の舞台としての伏見をアピールしていくことで、京都近郊からの旅行者の呼び込みにも力を入れていきたい考えだ。今年8月には、地元商店街、保勝会、酒蔵、観光協会などとプロジェクトチームを立ち上げ、具体的な取り組みについて議論を始めたという。
2ヶ所目は大原。昭和40年代には京都市のなかでも人気ナンバーワンの観光地で、若者の間で大原旅行は流行のひとつとなっていたが、現在は全盛期の3分の1ほどに減少しているという。京都の里山として、四季折々の風景が楽しめ、地元で採れる野菜も大原ブランドとして人気で、三千院や宝泉院など見どころも多い。しかし、問題はアクセスだ。京都駅からだとバスで1時間ほどかかってしまううえ、時間帯によっては渋滞に悩まされることもある。
そこで、京都市では、よりスムーズなアクセス方法として、地下鉄とバスが乗り放題になる「地下鉄・バス1日乗車券」の活用を国内外の旅行者に呼びかけている。大原へは地下鉄烏丸線の国際会館駅まで行き、そこからバスに乗り換え20分ほどでアクセスすることが可能。地下鉄は運行頻度も高く、渋滞も心配する必要がない。「地下鉄・バス1日乗車券」は今年3月に1,200円から900円に値下げされた。そもそもは混雑するバスから地下鉄の利用を促すための値下げだが、「近郊へのアクセスでも有効利用してもらいたい」と、今後PRを強めていく考えだ。
このほか、大野原、山科、京北などのエリアへの誘客も進めていきたい考えだが、観光素材がまだ未熟なことから、行政の取り組みとしては「まずはコンテンツ開発を進める事業者への支援がメインになる」という。
観光客に大人気の嵐山の竹林の小経。時間帯によって混雑具合は大きく異なる。上の写真が2018年4月の平日午前11時ごろ。カメラを構える訪日外国人でごった返す。下の写真は、2018年7月の平日午後6時過ぎ。観光客はまばらで静か。


民泊新法で健全な民泊が増加、住宅地のオーバーツーリズム改善へ
京都市では民泊もここ数年大きな問題となっている。住宅地に違法な宿泊施設が入り込み、マナー問題や防火対策などで周辺住民の不安は高まるばかり。その民泊施設に向かうために生活路線である市バスに大きなスーツケースを持ち込み乗車するため、通勤通学の足にも影響が出てきた。
京都市はこれまでに500軒以上の違法民泊を取り締まってきたが、「モグラたたき状態だった」(福原氏)という。旅行者が市民生活にオーバーフローすることで起こる「観光公害」は京都市だけの問題ではないだろう。
その違法民泊は、今年6月に施行された住宅宿泊事業法で風向きは変わった。京都市は全国でも最も厳しい条例を定めた。住居専用地域では、家主不在型の場合は1月15日から3月15日の60日間に限定。しかも、物件に10分以内で駆けつけなければいけない要件もつけた。一方、家主居住型は住宅宿泊事業法で規定された年間180日を認めることでメリハリをつけた。京町家については、保存も目的として、家主不在型の場合でも年間180日の民泊営業を認める。ただ、行政が伝統的な工法で建てられた京町家と認定した物件に限られる。この結果、今年7月13日現在、民泊申請数は87件で、受理されたのは47件。そのほとんどが家主居住型だという。
興味深いのは、旅館業法の簡易宿所の許可件数が2016年度で813件、2017年度で871件。総数が2291件であることから、過去2年間で急増したことになる。この背景にあるのは、「いわゆる民泊新法の動きと、インバウンドをビジネスチャンスととらえる動き、両方の影響だろう」と見ている。2017年度の京都市での宿泊人数は、実数で前年比10%増の1557万人、述べ人数で同13.7%増の2444万人と過去最高となった。これは、「簡易宿所の増加とリンクしているのではないか」との見立てだ。

用途規制の特例で郊外にホテル建設の動きも
簡易宿所や合法民泊、京町家の宿泊施設が増えているが、今後それだけで日本を含めた世界からの観光客を収容できるかどうかは分からない。京都市の方針としては、観光客の人数は追わず、観光の質を高めることで現地消費額を重視していく方針を打ち立てるが、行政が入洛数を制限することは、余程の力技がなければ不可能だ。
京都市では、将来の宿泊施設不足に備えるひとつの技として、ホテル建設での用途規制の特例扱いを昨年の5月から始めた。京都市内はほとんどが市街化調整区域で、用途規制上ホテルなどの商業宿泊施設を建設することに規制がかけられているが、そこに特例を適用する。ただ、厳しい条件をつけた。
富裕者層向けのラグジュアリーホテル、MICE向けのコンベンション施設を持つホテルなど京都市の施策に合致し、加えて地元住民の合意を取り付ける必要がある。この特例措置を市中心部の外で適用できれば、観光客の分散化にもつながると期待は大きいが、「実現には時間がかかる」との認識。すでに地元への説明会までこぎつけた案件はあるが、住民の合意形成が優先となるため、一朝一夕にはいかないのが現状のようだ。
門川市長曰く、「京都は観光都市ではない。京都の文化や歴史が評価されて、結果的に世界から観光客が訪れるようになった」。生活のなかにこそ価値がある。だからこそ、観光と生活との調和が大切になってくる。福原氏は「オーバーツーリズムに対する危機感は強まっているのは確か。しかし、事業者、住民、観光客、それぞれ立場によって意識はかなり違う」と明かす。それを調整していくのが京都市の大きな仕事になってくる。
『京都市の深掘り取材』、次回の第3回目は地元の生の声。観光客でごった返す嵐山の現状について、嵐山保勝会の石川会長に話を聞いた。
記事: トラベルジャーナリスト 山田友樹


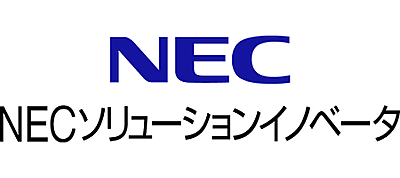

















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】