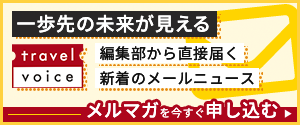観光庁、文化庁、スポーツ庁は第8回スポーツ文化ツーリズムシンポジウムを開催した。3庁は、スポーツや文化芸術資源の融合を通じて、新たに生まれる地域の魅力を国内外に発信し、訪日外国人旅行者の増加や国内観光の活性化を図るための政策連携の取り組みを進めている。
シンポジウムでは、3庁が連携をさらに強化していく目的で包括的連携協定を締結した。これは2016年に締結された連携協定に続くもの。今回の協定で、スポーツ、文化芸術および観光の相乗効果をさらに高め、世界に向けて地域ブランド、日本ブランドの発信を強化していく。
具体的には、文化芸術・スポーツを活用した観光コンテンツの開発や観光地域の高付加価値化、国内での国際的なスポーツ・文化芸術イベントを契機とした訪日機会や周遊機会の創出などを進めていく。
民間との連携をさらに密に
シンポジウムで3庁長官によるトークセッションも開催された。文化庁の都倉俊一長官は、「(訪日外国人は)モノを見て、体験する以上に、日本文化の背景にある精神性にものすごく興味がある。私たちは、その日本文化の重みや深さに自信を持って、そのまま紹介することを観光行政の基礎にすべき」と発言した。
一方で、大谷翔平選手、ウィンブルドンテニス、グラミー賞などが海外からの観光客を惹き寄せていることを例に出しながら、「日本は残念ながらソフトの部分の成長はまだまだという感じがする。本当は、日本はコンテンツ大国で、ソフトの宝庫。それらを観光資源として充実させれば、日本の観光の未来は明るい」と続けた。
スポーツ庁の室伏広治長官は、観光資源として日本武道について言及。2024年10月に仁和寺で開催された「BUDOツーリズムフェア2024」を例に、「体を動かすことと精神性が求められるスポーツは世界でも珍しい。こうした武道の文化とツーリズムを融合させるように取り組みにも3庁連携で取り組んでいきたい」と話した。
また、2025年は東京2025世界陸上、東京2025デフリンピック、2026年には第20回アジア競技大会(名古屋)が開催されることから、「海外からの来場者に日本の文化芸術も体験してもらえるように連携していきたい」と話すとともに、「デジタル化で紐づいていくようなネットワークを作り、情報がしっかり届けられるようすることも合わせて取り組んでいく必要がある」と続けた。
観光庁の秡川直也長官は、訪日市場で成果が出ているのは「民間の色々な取り組みがうまく噛み合っている結果。行政との役割分担で、この連携をさらに密にして、続けていくことが大切」と話した。さらに、「観光庁は、訪日外国人に地方に行ってもらって、楽しんでもらえるようにするのが役割。日本に行ってみたいと思わせるきっかけを担っているのが文化庁とスポーツ庁」としたうえで、「3庁のコラボレーションによって、もっと良い結果が出ると思う」と連携に期待を込めた。
スポーツ文化ツーリズムアワード2024を表彰
このほか、シンポジウムでは、スポーツ文化ツーリズムアワード2024の表彰式を開催した。表彰されたのは、本賞3団体と特別賞4団体。
本賞の「スポーツ文化ツーリズム賞」は、山形県飯豊町いいでまち商工観光課の「『白川湖の水没林』における『映える』カヌーツアーを主軸としたサステナブルな観光地づくり」が受賞した。
近年急激に人気を博した白川湖の水没林は未成熟な観光地としての課題があったが、カヌーツアーなどのウォータースポーツ体験が町の広告塔となり、地域の認知度や観光消費波及を牽引。また、湖岸でのアート作品の展示や、ライトアップの開催によって、新たな来訪者を獲得したほか、クリーンアップ活動などをおこなうことで、白川湖の特別な景観や、下流域の文化的景観、地元住民の生活を守りつつ、的確な情報発信などによって、観光消費を拡大させるサステナブルな観光地作りに取り組んでいる。
「スポーツツーリズム賞」は、サロマ湖100kmウルトラマラソン実行委員会の「サロマ湖の雄大なロケーションを舞台にした100kmの日本陸連公認レースウルトラマラソンの原点『サロマ湖100kmウルトラマラソン』」が受賞。
1986年から開催している100キロのウルトラマラソンは、毎年6月最終週に開催し、次回で40周年となる日本陸連公認レース。サロマ湖畔を舞台に、湧別町、佐呂間町、北見市の3自治体の合同事業に参加者4000名以上が現地を訪れることで、交通・宿泊のみならず様々な分野で経済効果を生み出し、日本最大級のイベントに成長している。
「文化ツーリズム賞」は、琵琶湖疏水沿線魅力創造協議会の「フィールドミュージアム『琵琶湖疏水』の魅力発信等による文化・景観や観光振興への貢献」。
琵琶湖疏水は竣工から130年以上経った今でも、京都の町に水を運び続ける重要な都市基盤となっており、その意義を伝えるため、1989年に琵琶湖疏水記念館を開館。2018年には、およそ70年ぶりの舟運復活となる琵琶湖疏水線の運行を官民協働のもとで成し遂げるなど、琵琶湖疏水の魅力向上、情報発信を行い、琵琶湖疏水沿線の魅力向上や文化観光の推進および沿線地域への周遊促進などの取り組みを推進してきた。
 本賞の受賞団体このほか、特別賞は、「日本遺産ツーリズム賞」として、日本観光振興協会の「日本遺産『御周印』(ごしゅういん)・『御周印帳』(ごしゅういんちょう)」、「食文化ツーリズム賞」として、新潟県観光協会の「地域の食文化を体現するレストランを起点とした旅を誘発する『新潟ガストロノミーアワード』」、「新しい観光賞」として、特定非営利活動法人AYAの「『挑戦!世界自然遺産・小笠原諸島へ大冒険!』医療的ケア児やその家族がリードユーザーへ!!」と、福岡よか街プロジェクト事務局の「ホーム・アウェイ関係なく福岡を楽しもう!『福岡よか街プロジェクト』~サッカー×地域資源×ユーザー投稿による街のにぎわい創出~」が受賞した。
本賞の受賞団体このほか、特別賞は、「日本遺産ツーリズム賞」として、日本観光振興協会の「日本遺産『御周印』(ごしゅういん)・『御周印帳』(ごしゅういんちょう)」、「食文化ツーリズム賞」として、新潟県観光協会の「地域の食文化を体現するレストランを起点とした旅を誘発する『新潟ガストロノミーアワード』」、「新しい観光賞」として、特定非営利活動法人AYAの「『挑戦!世界自然遺産・小笠原諸島へ大冒険!』医療的ケア児やその家族がリードユーザーへ!!」と、福岡よか街プロジェクト事務局の「ホーム・アウェイ関係なく福岡を楽しもう!『福岡よか街プロジェクト』~サッカー×地域資源×ユーザー投稿による街のにぎわい創出~」が受賞した。
 特別賞の受賞団体
特別賞の受賞団体


















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】