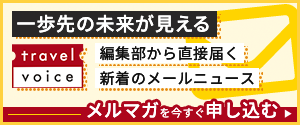一般的に、総務の仕事とはどういうイメージだろうか。組織運営そのものに関わるさまざまな業種を担当する、「縁の下の力持ち」と表現されることも少なくなく、それは国の観光庁においても同様だ。
トラベルボイスの「観光庁の未来を、観光庁の課長に聞く」インタビューシリーズ。第5回目となる今回は、予算、文書管理、国会対応、人事、法令、広報などを所管する観光庁総務課の課長である桑田龍太郎氏に聞いてきた。実は総務課は、防災・危機管理も担当しており、能登半島地震でも緊急対策のために観光庁内の多岐にわたる事業を即座に把握しつつ、各省庁、地域と調整しながらコントロールする大きな役割も担ってきた。こうしたさまざまな取り組みから、観光、そして地域が新生を果たすための地道な活動が浮き彫りになった。
能登半島地震で取りまとめに奔走
能登半島地震が発生した2024年1月1日。観光庁総務課は桑田氏をはじめ、防災危機管理担当中心に即座に動いた。国・政府にすぐ非常対策本部が立ち上がるとともに、観光の観点であらゆる角度から情報を整理。「特に情報弱者である訪日外国人観光客に対する災害・安全情報の発信、観光客の安全確認、宿泊・観光施設の被害情報・復旧復興といったさまざまな危機管理について、訪日外国人観光客の対応は国際観光課及び外客受入室、宿泊施設の対応は観光産業課及び産業競争力強化室といったように各課室に動いていただきながら、正月三が日から無我夢中で対応してきた」。桑田氏は噛みしめるように振り返る。
初動対応後も、特に石川県能登地域では多くの住宅が被害を受けて避難生活が続いたため、影響が少なかったホテルや旅館の客室を確保して被災者を受け入れるための奔走が続いた。当時、被災者からは「ようやく畳の上の布団で眠ることができた」「プライバシーが確保された」との声も多く挙がっており、観光産業がこうした力を発揮できると印象づけた。しかも、安全性を確認しながらの風評被害対策に加え、需要の落ち込みを少しでもサポートするための「北陸応援割」の制度設計も急がなければいけなかった。
「3月に入り、石川、富山、福井、新潟にわたる北陸応援割を利用して多くの観光客が訪れるようになった一方で、和倉温泉をはじめ、能登地域では再開に至っていないエリアも少なくない。現地と密に調整し、連携しながらどう寄り添っていけるか。重責を担っているという緊張感は、いまなお継続してやむことはありません」(桑田氏)。
業務能力を最大限発揮できる環境づくり
こうした機動的な業務はもちろん、予算、人事、定員、国会対応でも観光庁において総務課は中核的な役割を果たしている。
2008年に発足し、昨年10月に15周年を迎えた観光庁。東日本大震災、コロナといった需要が急減する災禍に幾度となく翻弄されつつも、観光立国への潮流、地方創生への期待を受け、当初100名程度だった職員は現在、出向者も含めて約300名にまで増強されている。このうち、総務課は40名程度を占める。
桑田氏は「観光というのは、さまざまな省庁、そして地方、民間企業も含めて横断的に取り組まなければならない分野であり、観光庁には多様な人材が集まってきています。総務課は人事全体をレイアウトする調整役。皆が国の観光の未来に向け、仕事を楽しみ、能力を発揮するとともに向上できる環境づくりが不可欠だと考えています」と力を込める。
「稼ぐ力」を磨くための予算の読み方とは?
とりわけ、観光産業に従事する事業者、DMO、自治体にとって重要なのは、総務課が観光庁の予算を主管している点であろう。
観光庁の2024年度(令和6年度)の予算は、前年度比1.64倍の約503億円。2023年度(令和5年度)補正予算の活用も併せて、「持続可能な観光地域づくり」、「地方を中心としたインバウンド誘客の戦略的取組の推進」、「国内交流の拡大」を3本柱に、多くの補助事業が展開されている。事業者、DMO、自治体にとって、やるべきことを自分たちで考えて行動できる自走する組織づくりはもちろん、こうした予算、支援を自分たちの成長領域、課題に合わせて、最大限活用していくことも不可欠である。では、観光産業に従事する人々はこうした予算・支援をどう読み解いていったらいいのだろうか。
「個別の予算だけをみていくと、バラバラで理解しにくい印象があるかもしれません。意識していただけるとうれしいのは、2023年3月にアフターコロナに向けて策定された観光立国推進基本計画のテーマに基づいた予算が組み立てられていること。たとえば、3本柱の1つである持続可能な観光地域づくりを挙げると、各地固有の文化や自然を大切に活かす観点や、オーバーツーリズムのような住民が離れていく事態を防いで地域と共存する観点、人材の確保や事業経営面で産業として持続できるようにする観点など、様々な観点から持続可能性を追求する必要があります。地域が何を目指すのか目的を明確にし、ビジネスとして『稼ぐ力』をいかに蓄え、発揮していくか。予算の背景、狙いを全体ストーリーとして考え、より付加価値の高い観光客を呼び込んでいくための方策を地域全体で考えていただきたい」(桑田氏)。
また、観光庁のウェブサイトには、観光を通じた地域活性化を図るために、観光関係者のみならず、地域住民も連携して「住んでよし、訪れてよし」の地域づくりを実践していくための関係府省庁の支援施策も取りまとめられており、桑田氏は「ぜひ活用してほしい」と呼びかける。
2024年度の予算503億円のうち、403億円は、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るために日本から出国する旅客1人あたり1000円を徴収する国際観光旅客税が財源だ。観光庁を中心に国際観光振興にかかわる各省庁に割り当てられる。桑田氏は「インバウンドが好調で財源は復元しつつありますが、日本人の海外旅行の回復の遅れもあって、なかなかコロナ前には戻りません。インバウンド、アウトバウンドのバランスも大きな課題だと認識しています」と気を引き締める。
観光は地域の日常を変えるゲームチェンジャー
桑田氏は島根県浜田市出身。国土交通省、観光庁で要職を務める過程で、2016年の熊本地震の前から4年間にわたり、大分県大分市の副市長も務めてきた。その後は内閣府地方創生事務局と、まさに地方創生に中央、地域それぞれの立場から深く関わっている。いまや観光立国のキーワードとして欠かせない地方創生についてはどう見ているのだろうか。
「今後の少子高齢化で人口減少は避けられず、消滅する可能性がある自治体、限界集落の議論も広く叫ばれています。交通利便性、教育環境等に優れる都市部への集中が避けられない面も強いですが、たとえば大分市では中心市街地のにぎわい活性化を大分県内から県外への人口流出のストッパーにできるよう取り組んできました。一方で、観光は、定住人口の減少に関わらず工夫次第で多くの人を外から呼び込むことが可能であり、その地域の日常を変えるゲームチェンジャーとしての力、攻めていくことのできる力になります。地域資源を磨くことによる可能性は大きく、観光行政としてもしっかりと地域に寄り添いながら、地方創生に尽力していきます」(桑田氏)。
観光庁の組織から予算、人事、危機管理まで、黒子でありつつも実はオーケストラの指揮者のように、観光庁全体を束ねながら政策を進めている総務課。観光が新生を果たすため、地域が成長軌道への一歩を踏み出すため、重要な役割を果たしている。


















 観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】
観光マーケティング実務スタッフ(旅行好き大歓迎!)【株式会社マーケティング・ボイス】